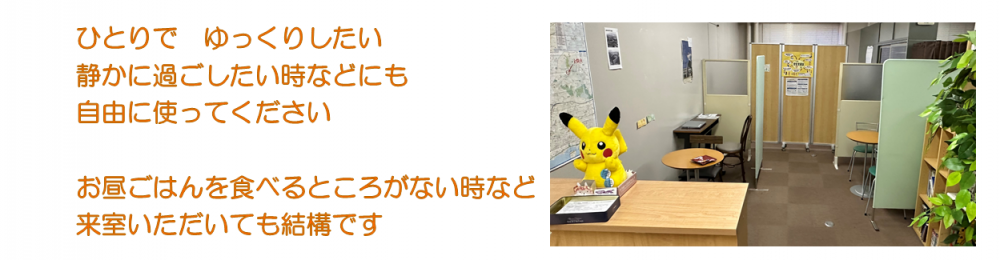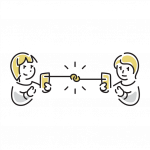地震や津波、台風や大雨などによる災害はいつ起こるかわかりません。大きな災害が起きた場合には、食料や生活スペースの確保、情報収集や連絡手段を把握しておく必要があります。
地震や津波、台風や大雨などによる災害はいつ起こるかわかりません。大きな災害が起きた場合には、食料や生活スペースの確保、情報収集や連絡手段を把握しておく必要があります。
ここでは、一人暮らしの大学生が備えておくべき防災対策として、重要なものをいくつか紹介します。
【防災用品】
・食料品
長期保存や携帯が可能な非常食を少なくとも3日分用意しておきましょう。レトルト食品や缶詰、ビスケットなどがおすすめです。その他、栄養補助食品や野菜ジュース、飲料水は1日あたり2リットルを目安に用意しておくとよいでしょう。
・衛生・生活用品
ウエットティッシュや絆創膏、常備薬やアルコール消毒液、マスクや歯磨きシート、非常用トイレ、女性は生理用品、必要に応じて使い捨てコンタクトレンズや眼鏡も用意しておくと便利です。
・貴重品
現金やマイナンバーカード、身分証明書などはまとめて保管し、すぐ持ち出せるようにしておきましょう。銀行やATMなどがストップし、キャッシュレス決済が対応できない可能性がありますので、小銭も含めた現金があると安心です。
・その他
懐中電灯、電池、手動充電式ラジオ、モバイルバッテリー、防寒具、カイロ、軍手など
【避難所やハザードマップの確認】
まず把握しておきたいのは家から一番近い避難所です。多くの場合、学校や公民館など自治体が指定する公共施設です。各自治体のホームページから確認できますので、避難ルートとあわせて把握しておきましょう。
また、避難場所・避難ルートとともに確認しておきたいのがハザードマップです。
災害が起こった際の避難想定区域や避難場所などが記されていて、災害時にどのあたりがより危険な地域なのかがわかります。
【連絡手段と安否確認方法】
災害が起これば電気やネットが使えなくなることもあります。携帯電話が使えなくても連絡ができる方法を確認し、家族や大切な人などの連絡先は紙に控えておきましょう。
・災害伝言ダイヤル(171)
NTT東日本により提供される声の伝言板です。固定電話をはじめ、携帯電話とPHS、公衆電話、災害時に避難所に設置される特設公衆電話で利用できます。1回あたり30秒の伝言が登録でき、登録できる最大の伝言数はひとつの電話番号あたり20件までです。
・災害伝言板(web171)
災害用伝言板は、インターネットを利用して被災地の方の安否確認を行う伝言板です。電話がつながりにくい場合でも、回線の集中を避けて安否情報の登録と確認ができます。インターネットが利用できる携帯電話やタブレット、パソコンなどで利用でき、1伝言あたり100文字のメッセージが登録可能です。
・公衆電話
公衆電話は災害時に通信規制の対象とならないため、携帯電話や自宅の固定電話が使えないときに役立ちます。停電の影響を受けることもありません。
・災害用アプリ
災害用の専用アプリならグループチャットで状況を確認できたり、位置情報を共有できたりなど、さまざまな方法で安否確認が行えます。アプリはキャリアのメールサーバーを使用しないため、通信が制限されている状況下でも利用が可能です。
・SNS
LINE、X、Facebook、Instagramなどに投稿しつながりのある人に安否を知らせることができます。ただし、通信環境の悪化や不確かな情報も含まれる可能性があるため、他の連絡手段も併用することがすすめられています。
9月1日は防災の日です。
この機会に災害の対策について考え、自主的に準備をしておきましょう。
参考文献:東京備蓄ナビ、安否確認Navi